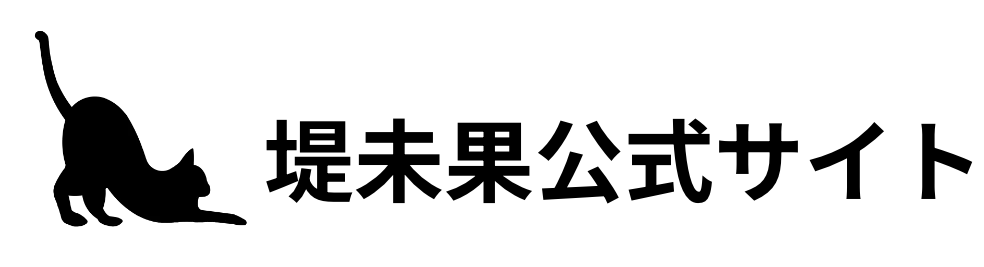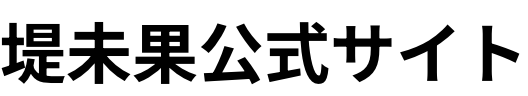ジャーナリスト 堤未果
2015年は、温室効果ガス排出削減を国際的コンセンサスとする潮流と共に幕を閉じた。12月12日。第21回国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP21)が採択したのは、地球温暖化対策における2020年以降の新たな枠組みとなる「パリ協定」だ。
今世紀後半までの「ゼロ炭素化」を求める同協定は、温室効果ガス削減を先進国に課する京都議定書と違い、国連に加盟する全196ヶ国に対し法的拘束力を持つ。そして2016年1月16日。この流れに沿うようにして、国際再生可能エネルギー機関(IRENA)が、再生エネルギーの使用が、気候変動だけでなく経済効果にも大きな影響を与える事を示す試算を発表した。それによると、2030年までに風力や地熱、水力や太陽光、バイオマスなどのエネルギー使用率を現在の倍に増やすことで、世界の総GDP額が約1兆3,000億ドル増加、雇用も拡大し、化石燃料の輸入にかかる政府支出も減るという。
エネルギー輸入大国である日本が再生エネルギー使用率を倍増した場合、そのGDP増加率はトップのウクライナについで160ヶ国中2位だ。
IRENAへの分担金出資比率が最も高いアメリカでは、再生可能エネルギー利用率100%を目指す自治体が少なくない。カリフォルニア州サンフランシスコは2020年、同サンディエゴは2035年までに、全ての電力を再生エネルギーに置き換えるという目標を掲げている。ハワイの州議会は2045年までに州内の電力を100%再生エネルギーでまかなう法案を可決した。
再生エネルギー自体への投資も増えている。ブルンバーグのデータによると、2015年の世界における再生エネルギー向け投資額は、原油価格下落や欧州経済悪化などにも関わらず、2004年の6倍である3293億ドルに達した。
環境問題の世界的権威である米国の思想家レスター・ブラウン博士によると、米国金融市場では30年以上前から原発への投資がない代わりに、再生エネルギーへの投資が数十億ドル規模で拡大しているという。博士は新著「大転換」の中で、再生エネルギーへの転換と投資が、今の時代にとって経済的にも必然だと説く。
だが新しい潮流は常にその規模と、生み出される利権の大きさが比例する。
例えば2012年7月から日本で実施されている「再生エネルギー固定価格買い取り制度(FIT)」もそのひとつだろう。太陽光発電で作られた電力を、電力会社が1キロワット42円という、諸外国の倍値で買い取ってくれる制度だ。この買取価格を決定した政府委員会の委員長は、その後偶然にも自然エネルギーの公益財団法人理事 に就任している。当時史上最悪の原発事故を起こした日本で、反原発運動の急激な高まりと共に成立したこの制度、外資規制が緩い日本で認可時点の買取価格が20年保障されるという破格の特典に外国人投資家達が即飛びついた。
この制度が導入されて以来、外資を中心に太陽光電力事業者が殺到した。だが買取価格が日本国民の電気料金に上乗せされる一方で、外資事業者の利益は国外へと流れる構造に、年々批判と見直しを求める声が高まっている。
一体私たちは何のために、石油依存からの脱却を目指すのか?
次なる巨大利権への乗り換えに持続可能社会を目指すという本来の目的がのまれぬように、原点に戻り再考したい。
週刊現代「ジャーナリストの目」2016年2月号掲載